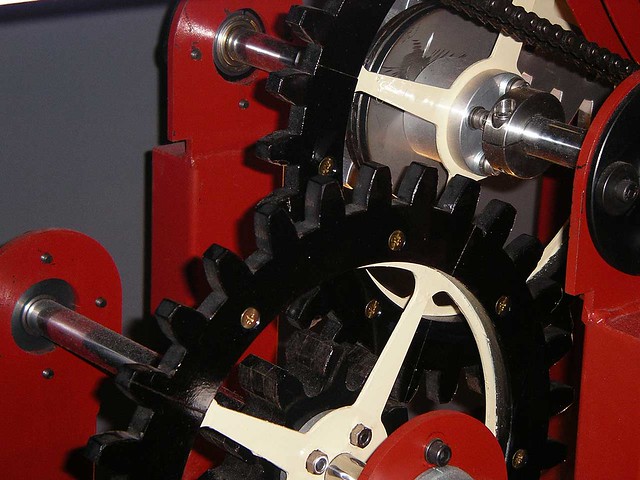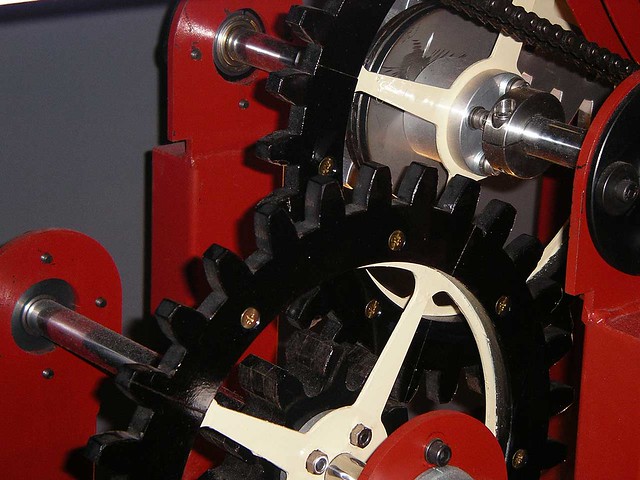
「頑張る」がもつ含意、表面にはあらわれない、もうひとつの意味についての歴史的な考察です。
きょうもがんばろう!そう言って日々頑張っているあなたは、いったい誰のために頑張っていますか?
頑張らなければ、正しい姿であらねば、こうしなければ、…という圧力に日々さらされている現代日本人、とりわけ、社会や組織のなかでその圧をいちばん強く受けている、若者と女性に向けて書きました。
「頑張りすぎないママが好き」と題した、月刊誌ヴェリィ(VERY)編集長、今尾朝子さんのコラムを読みました(朝日新聞2018年1月6日p21)。
今尾さんは、
昨年を振り返ってみると、ママたちに「頑張ろう」というより、「頑張らないで」というメッセージを伝える機会が増えた一年だったなと思います。
と書いています。何故か。ママたちが頑張りすぎているから、だそうです。いまどきのママたちは、
自分がやらなければ、家庭が回らないことが多すぎる。育児休業から復帰したからには仕事だって頑張りたい。自分自身に完璧を求めるつもりはなくても、周りができているであろうことができない自分に罪悪感を覚えてしまう。
という心境なのだそうです。
では、「頑張る」とは、一体全体どういうことなのか。これが、今回の主題です。
広辞苑(第6版・2008年)では、
①我意を張り通す。「まちがいないと─・る」
②どこまでも忍耐して努力する。「成功するまで─・る」
③ある場所を占めて動かない。「入口で─・る」
となっています。
現在、多くの人たちはおそらく、②の「どこまでも忍耐して努力する」の意味で、この「頑張る」という言葉を使っている、と思っているはずです。
数年前から僕は、この「頑張る」というコトバの、歴史的変遷や時代との連関、日本社会における意味などについて、明治以降の文献を手がかりに調べていますが、そこから見えてきたことです。じつは、いま一般的に使われている「頑張る」の本当の意味は、「忍耐して努力する」では、ありません。
「頑張る」に、もっとも必要なのは、一種の「自己犠牲」の要素です。自分を犠牲にして、「誰か」(←これも問題、後述)のために献身的に努力する行為(もしくは、そのフリ)こそが、現代日本で日常語と化した「頑張る」の本質なのだと、僕は考えています。
別のいいかたをすると、役割を果たす(もしくは、そのフリ)、ということです。母親として、妻として、働く女性として、求められた役割をきちんと果たす、期待に応えることが、頑張る、ということです。頑張る行為には、「正しさ」が求められます。だから、できない自分に罪悪感を覚えてしまうのです。
今尾さんは、こうも書いています。
自分のために頑張りたいときは必死になればいいけど、ママだけが頑張りすぎて疲れてしまうのはちょっと違う。
たしかに、ちょっと違います。自分のために頑張るのは、本当の「頑張る」では、ありません。いや、それも違います。
元来の「頑張る」は、まさしく、自分のために頑張ること、だったのですが、いま使われている「頑張る」は、多くの場合、自分以外のために頑張ることです。
もちろん、人のために頑張ることは素晴らしいことですし、誰かに尽くすことで自身の喜びも得られます。現在、頑張る人といえば一般に、
職場でも家庭でも、頑張る人は尊敬され、重宝されます。
~矢作直樹『自分を休ませる練習』p16
という存在です。それはほんらい、自分がやりたくてしていることです。自発的に「やる気」を出し、積極的に取り組む姿が尊敬され、重宝されます。ですが、社会や組織でそれがデフォルト化されると、自律のふりをした他律的な行為となり、自発的な貢献を強要されることになります。自分らしくないのに自分らしく、という、奇妙なことになってしまいます。「頑張る」が重たいのは、努力する行為そのものが重たいということ以上に、自己犠牲を強要されるのが、とても重たいのです。自分らしさからどんどん乖離していくのが、辛いのです。だから、頑張りすぎて疲れてしまうのです。
「誰」のための頑張りなのか、というのも、重要な点です。僕らが「頑張る」とき、しばしば、自分のためでも、特定の誰かのためでもなく、世間体とか、体裁とか、そんなものをとりつくろうために、「頑張る」を口にしていませんか。「頑張る」が美徳になって以降、頑張っている人を嘲笑するようなことは、なくなりました。かつて、「あいつ、頑張ってるな」は、「あいつ、まだ強情を張ってるのか」といった、呆れや、嘲笑のニュアンスがありましたが、いまは、とにかく頑張ってさえいれば、つまり、頑張る姿を示したり、「頑張ってます」と言ったりしていれば、人から悪口を言われることはありません。…という、いわば社会生活を営む上でのタテマエ的な挨拶言葉として、「頑張る」が使われているケースが、ふだんの生活ではよくあるように思います。
ところで、頑張っている人のことを、「頑張り屋さん」と言ったりします。現在、この「頑張り屋さん」は、好意的に使われていて、「あの子はほんとうに頑張り屋さんで」などと褒めたりします。ですが、かつての「頑張り屋さん」は違います。
「鉄道王」とも呼ばれた実業家、初代根津嘉一郎氏は、財界きっての頑張り屋さんとして有名でした。戦後、昭和27年の雑誌に、「頑張り屋、根津嘉一郎」という記事が載っています。ここでは、根津について、
根津さんは頑張り屋として聞こえていた。生まれたままの大きな赤ん坊で、何事にも、また何人にも、対手{相手、の意}かまわずガムシャラに突っかかっていた。
・・・
その生地がむきだしのところが、当時の財界では全く特異な存在であった。
と書いています。いま読むと、なんだか違和感があります。
戦前の雑誌記事では、根津氏のことを、「一旦言ひ出したら断じて後へは引かぬガン張り屋」(昭和5年)と形容しています。つまりは、頑固一徹、頑固ジジイ。上記の広辞苑では、①の意味になります。自己犠牲の要素など、みじんもありません。むしろ自己主張。あくまでも我を通し、わがままで、ある意味、迷惑な存在です。
娯楽映画の世界では、主人公が奮闘するドタバタ喜劇もののタイトルに、「頑張る」をつけることがよくありました。管見の限りで最古のものは、昭和3年の映画「娘頑張れ」。当時の雑誌記事では、その内容を、「奇術を勉強して松旭斎豚勝の名を得た上村太吉は錦をかざって故郷の恋人お春のもとへ急ぐ……それからはギヤツグを用ひて独得の喜劇です」と記しています。この流れは戦後も続き、昭和38年には有楽町の日劇で、中尾ミエ、園まり、伊藤ゆかりによる、「頑張れ!ハッスル3人娘」と題した舞台が行われています。
かつての「頑張る」には、このように、ときに滑稽なニュアンスが含まれていました。年月の経過とともに、「頑張る」は180度の変化を遂げ、いまでは推奨される美徳となりました。
今尾さんが書く「頑張りすぎている」状況は、今に始まったことではありませんし、ママたちに限ったことでもありません。
横浜市の高校生、ペンネーム・横浜太郎氏の「ガンバレ」と題する詩(1989年)。
毎日ふつうに生きていたいのに
「ガンバッテ」がついてくる
「時間よ。ガンバッテ起きなさい」
「ほら、ガンバッテ食べなさい」
「行ってらっしゃい。ガンバッテネ」
〔略〕
「ガンバッテ ガンバッテ」と言われてるうちに
一息いれるまもなくて
からだの中を流れる血がだんだん濃くなって
鉛のように重たくなって
ガンバレナイ人はいつのまにか消えて
ガンバッタ強い人はもっとガンバッテ
〔略〕
毎日ふつうに生きていたいので
「ガンバレ」は嫌いです
この詩が発表された1980年代は、「頑張れば夢がかなう」とか、「あきらめなければ夢はかなう」といった、いまよく耳にする「成果にコミット」した励ましのフレーズが、さかんに使われるようになりはじめた時期です。その傾向が顕著になり、多くの芸能人やスポーツ選手、経営者らがインタビューなどでそのテの発言を多くするようになったのは、2000年代に入ってからです。
成功した人たちは、だいたいが頑張って成果を出してきた人たちですから、それはそれは頑張ってきたのでしょう。でも、成果をあげることが素晴らしい、ではなく、頑張るプロセスが素晴らしい、とするのは、読者がそうした夢物語、ファンタジーを求めたからでしょう。
いっぽう、1990年代初頭のバブル崩壊後、「頑張っても報われるとは限らない」職場の広がりとともに、鎌田實医師の『がんばらない』(2000年)を筆頭にした「頑張る」批判が、日本社会の一部に起こります。
一例を挙げると、
・教師は生徒に、「やれば、できる!」「頑張ってやりなさい」と励ますが、それを繰り返し聞かされていると、「できないのは自分の頑張りが足りないからだ」「自分がダメだからだ」と思い込む生徒がいる。(1995年、関根正明・武蔵野音楽大学講師)
・頑張る人を美しく表現することは、頑張れない人に×をつけ、頑張らなければならない構造を温存させる。なんとも残酷な言葉だ。(2000年、辛淑玉)
・頑張れば何でもできると思うのは幻想。一握りの成功者が「頑張れば夢はかなう」と言うのは傲慢。(2008年、山田太一)
などなど。
なぜ、こんなことになってしまったのでしょう。
ドイツと日本を比較した研究が、一つのヒントを与えてくれます。ヨーロッパ文学の小林康彦氏の論文「独訳が難しい日本語─頑張れ!」(2005年)によれば、言語的にユニークなのは「頑張る」ではなく、励ましの言葉「頑張れ」です。
和独辞典に出ている「頑張る」としてのドイツ語訳(〔略〕の8語)は、今現在頑張っている様子や過去に頑張ったことを説明・表現する場合、つまり「~は頑張っている」や「~は頑張った」というような場合には頻繁に、そしてごく自然に使われる。しかし、「頑張れ!」と激励・応援する場合にこれらの語が使われることはほとんどない。
小林氏によれば、ドイツ人は口を揃えて「ドイツ人は日本人のように何でもかんでも、頑張れとは言わない」と言い、そのうちの一人はユーモアまじりに、「それでも日本人に負けないくらい頑張っていると思うよ!」と返してきたといいます。
ドイツ人といえば、いわずと知れた「ゲルマン魂」。サッカーのワールドカップで見せる、ドイツチームの気迫と執念に満ちたプレーは、日本チームの比ではありませんから、「日本人に負けないくらい頑張っている」というのは、相当に謙虚な表現です。
そもそも、日本社会の日常生活のなかで「頑張る」や「頑張れ」が今のような意味で使われはじめたのは、僕の調べによれば、昭和にはいってからで、当時はその見本として、もっぱら欧米人が挙げられていました。
「戦の勝利は最後の5分間にある」の有名な名言で、最後まで頑張りぬく大切さを説いたナポレオンを筆頭に、「蓄電池一つに十五年」の発明王エジソン、「全英国を敵手に頑張り通して八年、つひに大英帝国最初の労働宰相たる栄冠を戴いた」ジェームズ・ラムゼイ・マクドナルド、などなど。
「頑張る」は当初、欧米列強に日本が肩をならべるために待望された、「舶来モノ」のメンタリティでした。同時期にしきりといわれた「日本精神」と同様、「お国の役に立つ、あるべき日本人像」が、当時の「頑張る」「頑張れ」には込められていました。
『しぐさの日本文化』で「頑張る」の考察に一章を費やした多田道太郎は、「頑張る」が好感をもって迎えられ、日常生活で多用されるようになったきっかけを、昭和11年のベルリンオリンピックでアナウンサーが絶叫した「前畑ガンバレ」だったとしています。それにちなんで、8月11日が「ガンバレの日」になっているようなのですが、これより前から「頑張る」が流行語だったことを、僕は当時の文献で確認しています。おそらく、多田少年(このとき11歳)にとって、「前畑ガンバレ」がよほど印象的だったことから、こうした見当になったのでしょう。ちなみに、このときの前畑ら日本代表選手のオリンピックでの活躍は、「わが日本の威力を全地球の上に輝かした世界的選手諸君」(当時の新聞投書)と国民に受け取られました。
自分のため、ではなく、お国のために、ガンバレ。同調圧力でデフォルト化された自己犠牲的な努力。「前畑ガンバレ」の翌年には日中戦争がおこります。とりわけ、日中戦争が泥沼して以後、太平洋戦争までの期間は、「頑張れ」の怒号が日本中を席巻しました。ここで、当初の語義とは真逆の「自己犠牲」ファクターが「頑張れ」に刷り込まれていったと思われます。
「頑張る」「頑張れ」が、心温かい言葉だった時もありました。戦後の高度経済成長期です。戦後の焼け野原からの復興を遂げた日本は、やがて、国をあげて豊かさに猛進する時代に突入します。その恩恵をもっとも受けたのは、貧しい人たち、恵まれない人たちでした。彼らが豊かさを手に入れていく合言葉として、「頑張る」「頑張れ」がさかんに使われました。
頑張れば、誰もが豊かになれる。幸せになれる。なんとかなる。そう思えた時代は、1970年代に黄金期を迎えます。「頑張る」「頑張れ」には、いまでも、その頃の優しさの名残があります。だからこそ、いっそう、残酷なコトバでもある、僕はそう思います。
戦時下の日本人は、頑張っても夢はかないませんでしたが、戦後再出発した日本人は、今度は、頑張って夢をかなえました。少なくとも、人々は、そう信じました。豊かになる、一等国になる、大国になる。その夢をかなえた人々は、自分たちが一丸となって頑張ったと信じた、社会のあり方や価値観を絶対視して、次の時代に継がせます。戦後高度経済成長以後に生まれ育った僕ら(僕は1965年=昭和40年生)は、それを受け継いだ世代です。
母が子に、おばあちゃんが孫に、「勉強でも何でも頑張りなさい。頑張ったら必ずいいことがあるから」と激励し、「頑張る」こと、続けることの大切さが、民間伝承のように語り継がれていきます。「何事も達成するためには頑張らなくてはならない」(『自分を変える習慣力、三浦将、2015年』)との思いが、僕らの心に定着します。
「頑張る」が提唱されだした昭和初期の段階では、推奨された「頑張る」は、それとはちょっと違うものでした。当時の大衆娯楽雑誌『キング』に、著名な建築家、伊東忠太の「最後の瞬間まで頑張れ」と題した一文が載っています。
欧米人の特性は我国民の夫れに比して著しい相違がある。彼等は恬淡寡欲に非ずして何処までも功利主義であり、従って随分執拗であり、往々悪辣陰険なる手段もやり兼ねぬ。外交上の問題に於ても、吾人がいつ迄も古武士流の徳義を固守しているが為彼等の翻弄する所となり失敗を蒙ること少なくない。
〔略〕若し我が国民がこの欠点を自覚し、百難に耐ふるの執念と、千辛萬苦を忍ぶ根気を養成し、小心大膽の精神を以て最後の瞬間まで努力をつゞけることが出来たならば、何事に於ても欧米諸国に一歩も譲る処は無いのである。
桜の花の散り際のように淡白で、ものごとに執着しない日本人にくらべ、欧米人は功利主義で執拗で手段を選ばない。…サッカーで言われる「マリーシア」(ずる賢さを意味するポルトガル語)を思わせます。勝つための頑張り、成果をあげるための頑張りが、当初は求められていたのですが、「タテ社会の人間関係」(中根千枝)の日本社会で庶民の間に深く浸透していくうちに、その意味が変容していったようです。
「頑張れ」という励ましは、言外に、価値観の共有を前提としています(=何を頑張るかなんて、いわずもがな!)。価値観を共有していた高度成長期(=みんなで豊かになるぞ!)なら、それでよかったのです。受験やスポーツ競技など、目指す方向が自明であるとき、「頑張れ」は強力な応援のフレーズになりえますし、実際、受験界では古くから「頑張る」「頑張れ」が使われていました。「ガンバリズム」という言葉も、管見の限り、昭和2年の受験雑誌が最も古い使用例です。
しかしそれは、自分で考え、行動する、自律的な個人のあり方とは、相容れないものです。吉野源三郎の『君たちはどう生きるか』は「僕たち人間は、自分で自分を決定する力を持っている」(漫画版p301)と説きますが、この本が出版された昭和12年には日中戦争が始まり、以後、多くの日本人が、「自分で自分を決定する力」を行使することなく、自主的思考が不十分で権威に追従したことで、結果、多くの戦争犠牲者を生むことになりました。
以前に僕は、
この国は、ひとりひとりが自分で考えて判断することよりも、既存の社会のあり方や価値観を疑いもなく受容し、規範を忠実に守り、求められた役割を忠実に遂行することを、推奨しつづけてきたのではないでしょうか。
と書きました。これは、教育心理学者の藤原喜悦氏の主張(1991年)を援用したものですが、この「既存の社会のあり方や価値観を疑いもなく受容し、規範を忠実に守り、求められた役割を忠実に遂行すること」こそが、まさしく、いま、ママたちばかりか、日本中の人々を疲弊させている「頑張る」の本質です。
頑張るとは、現在、多くの場合、求められた役割を忠実に遂行する=期待に沿う、なのであり、頑張れとは、求められた役割を忠実に遂行しろ=期待に沿え、なのです。
多田道太郎は、「頑張る」の考察のなかで、
結婚式を終えたカップルを駅頭におくる若人たちが、つい無意識に「頑張ってきてね」などという。結婚という事業も頑張らなければできないという、これは集団的無意識の表現なのであろうか。
~『しぐさの日本文化』講談社学術文庫、2014年、p33
と疑問をなげかけていますが、「頑張ってきてね」を「求められた役割を忠実に遂行してきてね」と言い換えれば、なるほど、皆ニヤニヤしながら激励をするわけだと、納得もいきます。
自発的な努力を期待する「頑張れ」圧力には、観客がスポーツ選手に叫ぶ「頑張れ」もあれば、互いに励ましあう「おまえも頑張れ」もありますが、日本社会を支配する「頑張れ」圧力は、基本的に、高いところから低いところに、目上から目下へと向けられます。年配から若者へ、強者から弱者へと向かいます。女性や若者が、もっともその圧力にさらされているはずです。だから、ママたちは頑張りすぎて疲れてしまうのです。
さらにいえば、高齢化社会とは、「頑張れ」圧力がそれまでよりも強力に作用する社会であり、放置しておけば、今後さらに強化される恐れがあります。
…という現状への危機感ともいえる言説が、いま、各所からあがりはじめているように、僕には思えます。
嫌なものは嫌だと言おうと。
僕の知人が先日、欅坂46の「不協和音」に出てくる歌詞「僕は嫌だ」に、
時代の同調圧に抵抗する若者の心を悔しいことに秋元康が見事に詞にしている。
と書いていました。
先日の新聞記事「(逃走/闘争 2018:5)働き方、「正解」に縛られない」(朝日新聞2018年1月8日p29)の見出しには、「「日本のため」より自分の声に正直に」
と書かれ、記事中には、元SMAPの稲垣吾郎、草彅剛、香取慎吾がサイトに公開した動画にある、
「逃げよう」「自分を縛りつけるものから」
という言葉を紹介しています。
「やりたくないこと やらない」(朝日新聞2017年3月13日p11)で、東大東洋文化研究所教授の安冨歩氏は、
システムに支配されないためには、システムの中にいる私たちが立場に縛られず、自分自身となることです。そして、一人ひとりがその場でシステムの要求に従わないようにするしかありません。「しないといけない」とプレッシャーを感じることは、しない。そして、「したい」と思うけど足がすくむようなことは、やるのです。たとえば、「専業主婦だから掃除しなきゃいけないのに、自分はできていない」と思って胸が苦しくなるなら、掃除なんてそこまでしなければいいんです。〔略〕システムを変えるには、ものすごいエネルギーがいります。でも、小さなボイコットが多発すれば、システムは作動不良を起こし、違う方向に動き出すんです。
と語っていますが、戦時下の国民は、じつは案外、システムを変えるほどではないにしても、この「小さなボイコット」をしていました(→「昭和18年7月の特高月報:かなり物騒だった戦時下の民衆」を参照)。
戦時中、旧制高校で「反骨バンカラ学生」だったという小川再治氏(元東京学芸大学教授)は、当時のこんなエピソードを書き残しています。
某高級軍人が当時一高を訪ねた時、「ゾル帰れ」の落書きがあったという話を聞いた。「ゾル」とは当時の高校生が軍人を指す蔑称だった。また、私は偶然浦和高校生が応召学生を送る集会を上野駅前で見たが、軍人が見たら立腹しそうな「大いなる自由を愛せ」の大のぼりが立っていた。
~『孤高異端』2008年、p93
戦時中に「大いなる自由を愛せ」とは、たいした度胸です。彼ら浦高生が掲げたように、僕たちも、自分を縛りつけるもの、既存社会が強要する規範、システムの支配をボイコットして、大いなる自由を愛しませんか。嫌なものは嫌だと、言いませんか。
小田嶋隆氏は、
我々は自分自身であることより、自分たちが帰属する組織の規範を強く意識している。
~朝日新聞20171212p37
と指摘していますが、その伝統は、そんなに古くからのものでも、日本民族に固有のものでもないし、ぶっちゃけてしまえば、僕らは、「自分たちが帰属する組織の規範」というタテマエに、日々忠実に生きているわけでもありません。
「頑張る」とは、ある意味、「頑張ってるフリ」、つまり、頑張るという「お約束」もしくは、「頑張っているプレイ」の面もあります。正しき美徳、タテマエとしての「頑張る」さえ口にしておけば万事オーライ、誰かのために献身的に努力するフリや、役割を果たすフリ。
もともと頑張るのが苦手で、「奮闘努力の精神に乏しく、遊惰安逸に流れ、飽きやすく諦めやすく、一念を通す粘り強さに欠けた国民性」の僕たちが「要領よくやってきた」という側面もあります(ですよね?)。頑張りすぎて疲れてしまう人は、おそらく、とても優しい人です。生真面目に、既存社会が設定した正解、あるべきモデル像で自分を縛りつけてしまっているのだと思います。
先日の新聞に掲載された、作家・朝井リョウ氏の寄稿から(朝日新聞2018年1月7日p7)。
嫌だと思ったことを嫌だと言っていいんじゃないかって。
・・・
俺が嫌だと思った言葉を受け流すってことは、次の世代にその嫌な言葉が流れ着くってことかなあって。
・・・
新しい方法で元号が変わるってなったとき、自分ももっと、自分なりのやり方で、嫌だと思うことにNOを突き付けていいのかもって思ったんだよね。
・・・
あらゆる変化は、分厚いように見えて実はとても柔らかい思い込みで編まれていた縄から私たちを抜け出させ、新たな選択肢に手を伸ばすきっかけをくれる。これまでそうだったのだから、それが世間の常識だからという呪いの言葉から解放され、自分だけの人生の形を追い求める号砲となりうる。
僕たちはきっと、もっと楽しく、生きられるはずです。
※続きを書きましたので、あわせてどうぞ。→「「頑張り圧」という悪弊、頑張らないという戦略」
※こちらもどうぞ。→「「頑張り圧」が日本社会に定着したのは70年代初頭:思考停止社会のルーツ」
※2018年1月11日22:00初稿公開、2018年1月14日15:20第二稿公開、2018年1月16日10:30タイトル変更、その他、随時微修正。